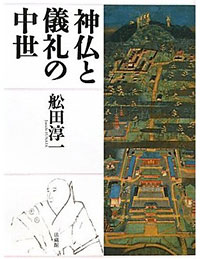神仏と儀礼の中世
儀礼の執行こそ、寺社という宗教空間の本質的機能であるという著者は、仏教と神祇の儀礼にかかわるものから中世的な神・仏の宗教世界に迫ります。
その舞台として南都の宗教界を取り上げ、中世には神仏習合が高度に発達したといいます。例えば、鎌倉前期の法相宗の僧侶貞慶は春日神の憑依・託宣を目の当たりにする宗教体験を契機に講式(儀礼のテキスト)を作成しており、同時代の華厳宗の僧侶明恵も春日神を祈念によって降臨させ、託宣を導きその真偽を決するという、シャーマニズム的な宗教体験に深く関わっていました。
中世南都律僧も戒律守護神として春日神を深く信仰しました。中世に活躍した律僧が、葬送を行いそのまま春日社に参拝したため、神はこれを厳しく咎めるものの、逆に仏教的な論理によって論破されるという説話もあります。また、人々の行為に目を光らせ厳格な賞罰を下すという任務には、その存在を可視的・感覚的に実感できる神が必要であり、これを律僧は「怒る神」として信仰しています。
中世の神仏習合は、庶民信仰的な世界ではなく、僧侶の神仏を探求する宗教的実践の中にあったことを教えてくれます。